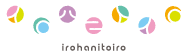vol.49-61 支援者が障害を作っている?!

支援しないという支援(6)
イロハに来てくださっている実習生(学生)の質問を使わせていただいて、
「支援しないという支援」についての具体例をお伝えしています
【質問2】
〇〇チームの人たちは仲がいいですね
どうしてそんなに仲が良いんですか?
イロハニトイロは、
螺鈿細工をしている「RADEN WORKS(螺鈿チーム)」
畑作業をしている「TANE WORKS(畑チーム)」
ハーブティのブレンド作業をしている「HAND WORKS(ハーブチーム)」
があります
学生さんには、各チームを回ってもらっています
そしてそれぞれのチームの雰囲気の違いを感じてもらっているのですが、
螺鈿チームの人たちが特にとても仲がよさそうに見えるそうなんです
そしてそれはメンバーの方々が優しいからなんだと思っているようです
ここでも「支援しようとしない支援」が説明できそうです
螺鈿チームが仲が良く見えるのは、皆さんが優しいから、
つまり、たくさん我慢して、相手を尊重し優しい態度で接しているから
というわけではないんです!
そして、スタッフから「仲良くすること」を強制されているからでもないんです!
仲良くしたくなければ仲良くしなくていいんです
自分の作品作りだけに取り組みたいのであればそうすればいいんです
他のメンバーとのつながりを絶ち切って作業に没頭してもいいんです
しかし、こういった意識での仕事の取組みが多くのトラブルが生んできました
多くの他者(他メンバー)への不満が態度や行動となって表出されたのです
ミーティングを開き、話し合いをしたいと決めてもほとんど人が集まらない
(7名中2名だけの参加ってのもしょっちゅう)
そうやって螺鈿チームのメンバーがたくさん困ったわけです
そして、そんな不満が渦巻く状態が続き、少しずつメンバーが思いを吐き出すようになりました
そして、
「どんな螺鈿チームになっていきたいのか?」
「それは何のためなのか?」
「仲が良く協力し合える螺鈿チームになることでどんな良いことが起こるのか?」
そんな問いかけだけを
スタッフとして投げかけさせていただきました
そして後はチームの中で試行錯誤をしていっていただいたのです
ただそれだけ
チームの担当スタッフは私(金村)でしたが、新しく立ち上がった内職チームの方で忙しく、螺鈿チームはほったらかし
やっていたことは、不満や訴えがあればただ受容的に聞くだけ
それ以外は何もしていません
スタッフが何もしなければしないほど、
チームの交流は活性化し、
チームはまとまり、
協力関係が増してきました
不満があるメンバーともどうすれば上手くやっていけるか
上手くやることはチームの利益になる
チームの利益は自分の利益にもなる
そういった意識を共有し、
メンバー同士で声を掛け合い進んできた結果が現在の状況であり、
学生さんから見るととても仲の良い雰囲気に見えているんだと思います
ちなみに現在は、月1回のミーティングは、全員参加が当たり前となっています
もちろん促しの声掛けなんてしていません
メンバー同士で声を掛け合っています
また現在、ある有名美術館(信楽)でイロハの作品を展示販売させていただいていますが、
それもメンバーさんたちの力で実現したことなんです
螺鈿メンバーの方々が、
奈良に移住された螺鈿の先生の所へ「研修に行きたい」とご希望され、
そして先生に自分たちの作品を見せたところ、
先生を唸らせ、
「これはもっといろんな人に見てもらわないといけない」と
美術館での展示販売に繋げてくださいました
そして、数か月に一度の美術館への納品の際もメンバーが主体となって取引先とやりとりをしてくださっています
スタッフが支援しようとしないからこそ
“困った”という不快が生まれ
“どうにかしよう”という思考が生まれ
実際に行動し
その結果を自信に変えて
次の行動のエネルギーにしていく
その行動の中でさまざまな知識や技術を身につけ
そして人との繋がりを強めていく
スタッフが何もしなければしないほど
スタッフがポンコツでいればいるほど
メンバーの方々の力がどんどん発揮されるようになる
つまり、スタッフはいろんなものから守る「壁」になるのではなく
メンバーが自由にダンスできる「床」になる
それが「支援しない支援」のような気がしています
次回、もう一つ学生の質問から「支援しない支援」について具体例を話させていただければと思います
イロハニトイロ所長
金村栄治